
━ 「灸花(やいとばな)」とは
「灸花」とは、植物ヘクソカズラ(屁糞葛)の別名です。
小さな花がお灸のもぐさに似ていることから、この名がつけられました。

アカネ科のつる性多年草で、夏の盛り、7月から9月にかけて花を咲かせます。
花は直径1センチほどと小ぶりで、外側は淡い紅色、中央には紅紫色の模様がくっきりと浮かび上がり、まるで小さなラッパのような姿をしています。
葉や茎をもむと独特の匂いを放つため、古くから「屁糞葛(ヘクソカズラ)」とも呼ばれてきました。道ばたや草むらなど身近な場所に自生し、日常の中でよく目にする野草のひとつです。
また、秋から初冬にかけてとれる実は、しもやけやひびなどの薬用として古くから利用されてきました。
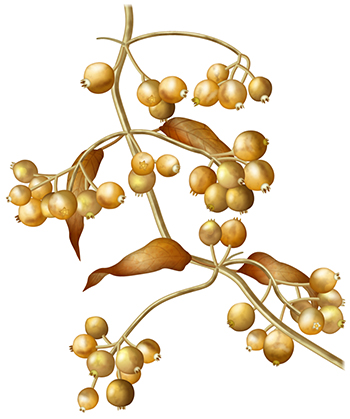
━ 夏の季語
俳句の世界では、「くそかずら」や「灸花」は夏の季語として使われています。
花の姿や名前の面白さに加え、昔から親しまれてきた植物だからこそ、多くの歌や句に詠まれてきたのでしょう。
━ 『万葉集』に詠まれた屎葛(くそかずら)
“茰莢(かわらふじ)に延(は)ひおぼとれる屎葛絶ゆることなく宮仕(みやつかへ)せむ” 高宮王
すでに奈良時代の『万葉集』にも「屎葛(くそかずら)」の名で詠まれています。
巻16・3855の歌では、女性が宮仕えの尽きることのない苦労を、この草のつるにたとえました。
どこまでも伸び、絡みつきながら繁茂していく屎葛の姿を、終わりのない勤めや苦労に重ね合わせたものです。
“名をへくそかづらとぞいふ 花盛り” 高浜虚子(たかはま きょし)
素朴で可憐な花姿と、花の名との取り合わせをユーモラスにとらえた一句です。
“蛇籠(じゃかご)より蛇籠へ渡り 灸花” 高野素十(たかの すじゅう)
石を詰めた蛇籠にからみつき、つるをのばして咲くヘクソカズラの様子を描いています。
━ 草花遊び「お灸ごっこ」
草花遊びに、お灸ごっこという遊びがありました。
ヘクソカズラ別名「灸花」の花のカタチが、お灸のもぐさと似ているところからつけられたようです。
一度つけると簡単には落ちないので、子どもたちは「アツ、アツ、」と声をまねしながら楽しんでいたそうです。ヘクソカズラ「灸花」が咲くこの季節ならでは、子どもたちのお灸ごっこだったのですね。
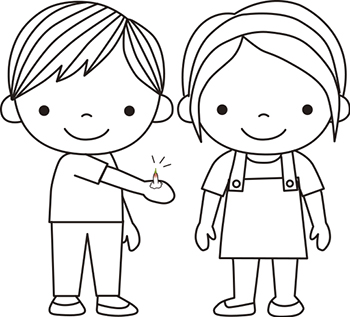
道ばたや草むらに咲く「灸花」。その花で遊ぶ子どもたちの姿を思うと、お灸がどの家庭でも身近なものだったことがうかがい知れます。










